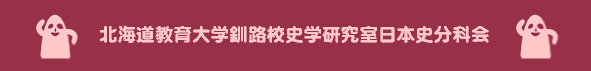
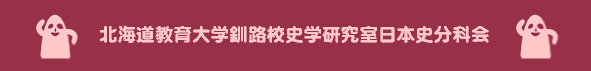
講義と免許
1.「専門」について
一般教養などの講義は、講義棟の大講義室などで行われますが、私たち学生が普段「専門」と呼んでいる演習系科目の場合、研究棟の史学研究室で行われます。私たち日本史分科会の場合は、史学演習室(A409)で行います。
では、専門はどのように行われるのかを紹介しましょう(詳しい課題などは別項にありますので、そちらをご参照ください)。専門は、その日の担当者(学生)が事前に調べてきたことを発表し、それについて教官や他の学生が様々な意見交換を繰り広げるという、いわゆるゼミ方式で行われます。
それでは、発表に至るまでの経過を順に追っていきましょう。まず事前に教官から、私たちに課題という名の「勅命」が下されます。時として、その勅命のあまりの重さに気を失うこともあるのですが(ウソ)、その勅命を遂行するために様々な方法を使って調べ、「レジュメ」というものを作ります。参考によく使うのが、「国史大辞典」(日本史に関することなら大抵のことが載っている)、「大漢和辞典」(漢語林のお父さんで、最強の漢和辞典)で、その他は課題の内容によって使い分けます。が、研究室にはいろいろな資料がありますので、先輩方に尋ねてみると良いでしょう。こうして、レジュメを作っていくのですが、レジュメとはいわゆる報告書みたいなものです。これを使って専門で発表を行うわけです。作業に取り掛かるのは、早ければ早いほどいいですよ。さもないと・・・。
2.日本文化史演習について
日本史分科会では、2年に1度、2年生と3年生の2学年合同で、春休みを利用して10泊11日程度の日本文化史演習(ゼミ研修旅行)を行います。行き先は学生が相談して決めますが、奈良・京都・鎌倉・東京になるケースがほとんどです。
2002年度の日本文化史演習では、マスコミ発表された翌日に、古代のカレンダーの木簡を飛鳥資料館で見ることができました。また、国立歴史民俗博物館や東京大学史料編纂所では、本物の歴史資料や、その調査・研究の様子を見学しました。日本史に興味がある人なら、研究したい時代に関係が深い土地で、多くの文化財や史料にふれることができるので、お金に換えることができない貴重な体験ができることは間違いないでしょう。
また日本文化史演習は、修学旅行とは違い、現地集合・現地解散という自主性に任された研修旅行です。ですから、修学旅行では訪れない穴場を自分たちのペ−スで見て回ること ができるので、大学生活におけるかけがえのない経験の一つになるはずです。
参考までに2002年度日本文化史演習の行程を下記に示します。
| 1日目 | 奈良(飛鳥地区) 橿原考古学研究所付属博物館->甘樫の丘->水落遺跡->国立飛鳥資料館-> 飛鳥坐神社->飛鳥寺->酒船石->伝飛鳥板蓋宮跡->石舞台古墳->橘寺-> 川原寺->亀石->高松塚古墳->猿石 |
| 2日目 | 奈良(奈良地区) 平城宮資料館->平城宮朱雀門->平城宮大極殿->平城宮発掘現場-> 平城宮東院庭園跡->興福寺->正倉院->東大寺->奈良国立博物館 |
| 3日目 | 京都(東山地区) 三十三間堂->京都国立博物館->清水寺->知恩院->南禅寺->銀閣寺 |
| 4日目 | 京都(洛北地区) 源光庵->北野天満宮->立命館大学国際平和ミュージアム->竜安寺->仁和寺 |
| 5日目 | 自由行動 関西もしくは関東 |
| 6日目 | 自由行動 関西もしくは関東 |
| 7日目 | 千葉 国立歴史民俗博物館 |
| 8日目 | 鎌倉 高徳院(鎌倉大仏)->長谷寺->鎌倉国宝館->鶴岡八幡宮->建長寺-> 明月院->圓覚寺 |
| 9日目 | 東京 防衛庁市ヶ谷記念館->東京大学史料編纂所 |
| 10日目 | 東京 江戸東京博物館->解散 |
2006年度日本文化史演習 フォト紀行
2004年度日本文化史演習 ビデオ紀行
|
|||||
|
|||||
|
3.取得免許について
史学研究室に所属すると、真面目に単位を取っていれば、以下の免許を取得することができます。
◇小学校1種
◇中学校(社会)1種
◇高等学校(地理・歴史)1種
その他にも余裕のある人は、自分の好みや努力次第で、様々な免許・資格が取れます。以下は、所属学生が取得した免許の例です。
△養護学校2種
△幼稚園1種
△中学校(理科)1種
△高等学校(公民)1種
△学芸員
いずれにしても、多くの免許を取りたい方は、早めに対策をとった方が良いでしょう。